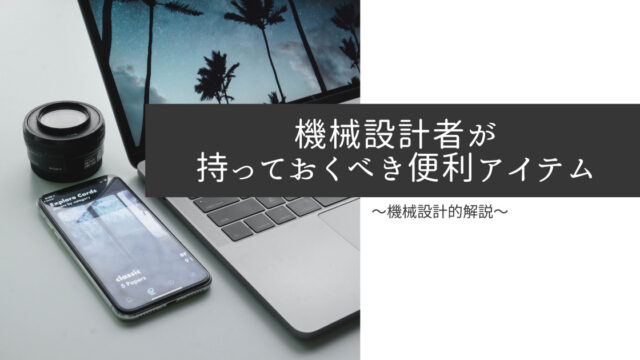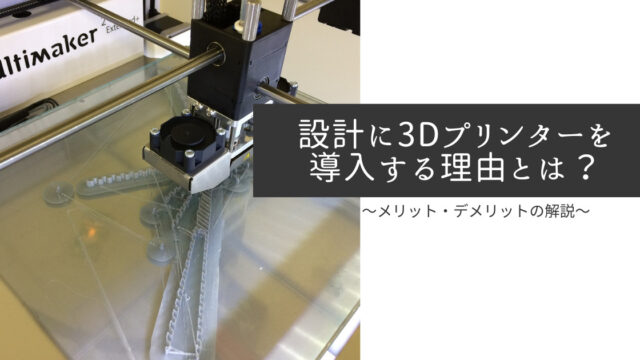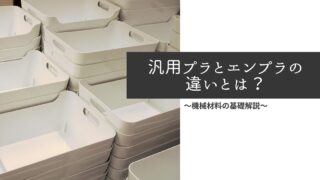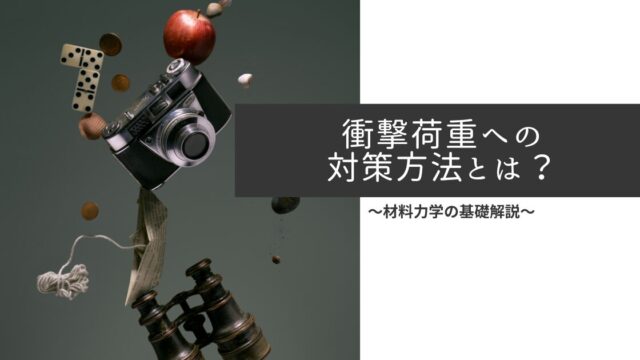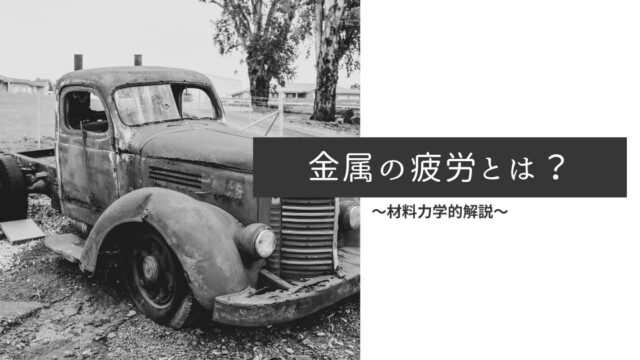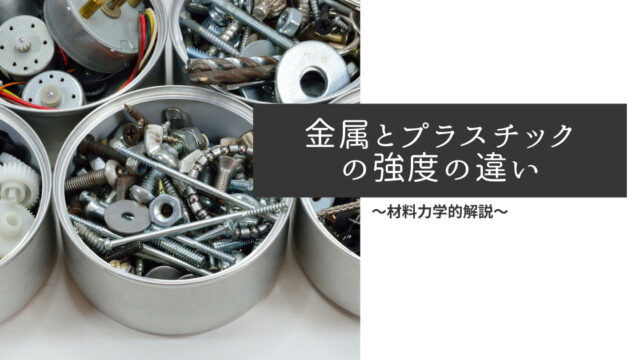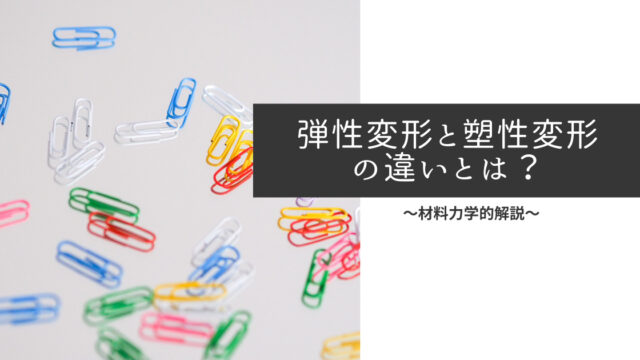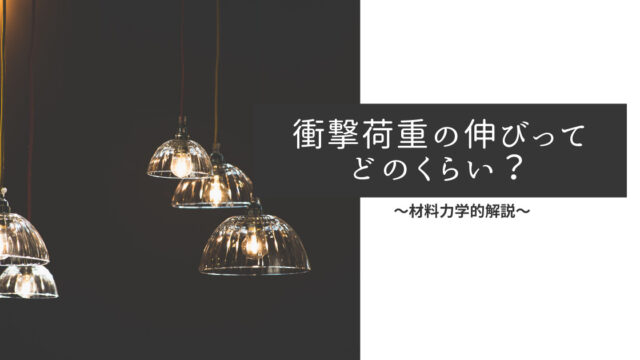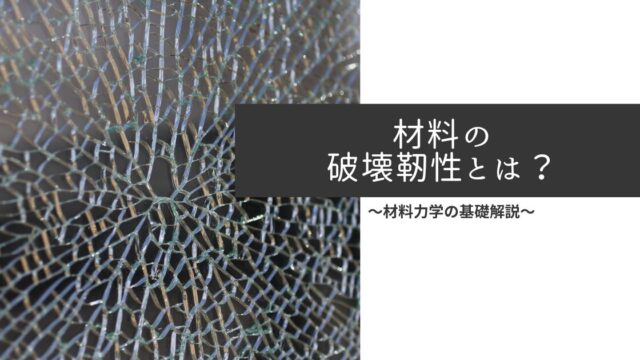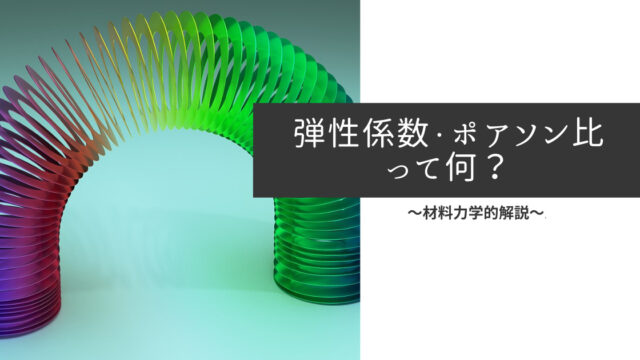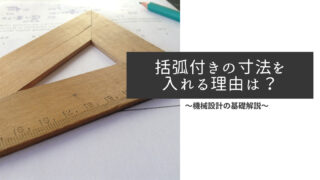機械の軽量化に適した材料とは?【材料選定の基礎解説】
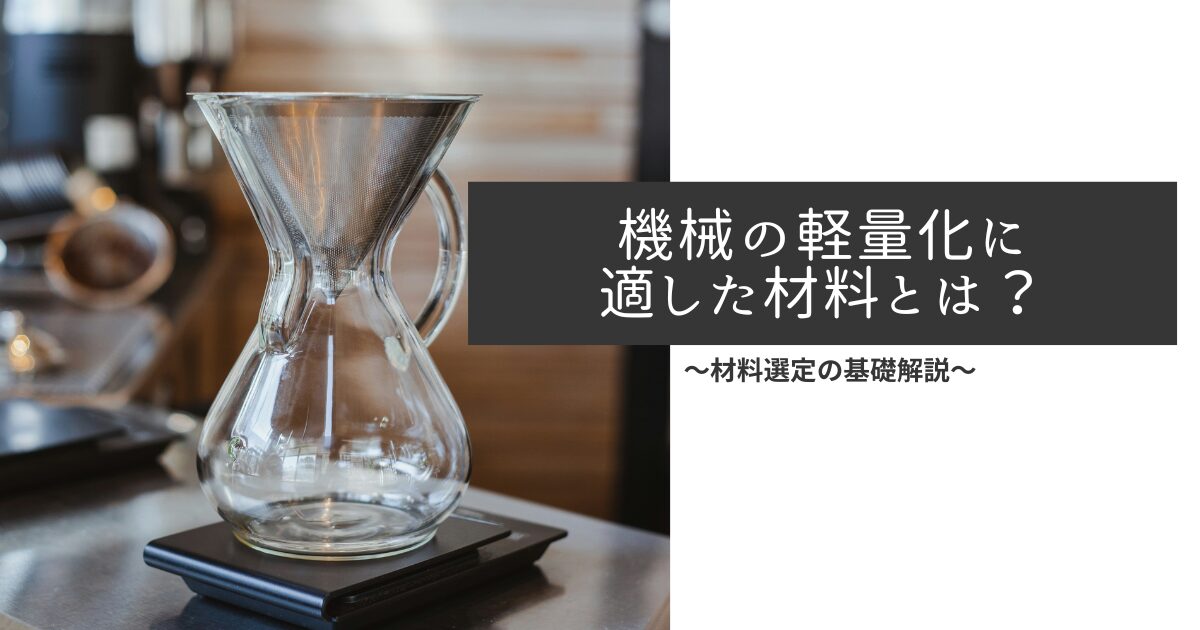
皆さんは機械の軽量化を行ったことはありますか。
軽量化設計は、現代のエンジニアリングにおいて重要なテーマの一つです。
今回は軽量化設計を進めるにあたって考慮すべきポイントを解説したいと思います。
軽量化設計の意義とは
軽量化には様々なメリットがあります。
エネルギー効率の向上
製品が軽くなることで、輸送時のエネルギー消費を削減することができます。
例えば、手で1個10kgの製品を運ぶ場合を考えてみましょう。
一度に10kgしか運べない場合、製品が100個あったとき、100往復必要になります。
ここで、製品の質量を5kgまで軽量化できた場合、半分の50往復で済みます。
車や飛行機で運ぶ場合も同様に、燃費が向上し、エネルギー効率が上がります。
性能の向上
質量が小さいことで、製品の使用性が向上します。
例えば、スマホを考えてみましょう。
スマホの質量が重いと、持ち運びしにくい、長時間の使用時には手が疲れてしまう、などのデメリットがあると思います。
できるだけ軽くすることで、製品を使いやすくすることが可能となります。
環境負荷の低減
製品を軽量化することで、製造時や廃棄時の環境負荷低減にも寄与することが可能です。
例えば、今まで金属で作っていた部品を、熱可塑性プラスチックに変更することで、部品のリサイクルが可能となります。
材料選定のプロセス
軽量化設計の材料選定は、以下のステップで進めます。
要件の明確化
使用するにあたって必要となる材料特性を決めます。
例えば、力がかかる場所であれば引張強度を、放熱を促す部品であれば熱伝導率が重要な特性となります。
その他にも、材料のコストや入手性、耐環境性などが挙げられます。
候補材料のリストアップ
軽量化可能な材料をリストアップします。
例えば、軽量かつ高強度な金属であれば、チタン合金が挙げられます。
非金属であれば、エンジニアリングプラスチックや炭素強化プラスチックなども候補となります。
金属や非金属などの枠組みに拘らず様々な視点から調査することが必要です。
候補材料の比較評価
要件と候補材料の特性を比較します。
密度が低い材料ほど軽量化が可能となりますが、使用環境に応じた材料を使用することが重要です。
特性だけでなく、製造プロセスや加工性の比較も行いましょう。
材料の選定
比較を行った中で、最も条件に合致する材料を選定します。
複数種類ある場合は、コストも考慮することが必要です。
軽量化材料例の特性と用途
軽量化材料の例を以下に記載します。
アルミニウム合金
鉄よりも軽く、加工性も良好です。
耐腐食性にも優れており、自動車のフレームや航空機の構造部品に使用されています。
マグネシウム合金
非常に軽量で、比剛性も高いです。
家電製品やモバイルデバイスに使用されていますが、耐腐食性が劣るため、表面処理が必要となります。
チタン合金
高強度で耐腐食性にも優れています。
軽量で高強度なことから、航空機のエンジンや高性能スポーツ用品に使われています。
しかし加工が難しく、高価でもあります。
炭素繊維強化プラスチック
炭素繊維が含まれていることで、プラスチックの強度を上げています。
レーシングカーや自転車のフレームにも使われていますが、リサイクルしにくく、高価という欠点もあります。
エンジニアリングプラスチック
耐衝撃性や耐薬品性が高いプラスチックのことを指します。
電子機器などに使われていますが、汎用プラスチックと比較して高価となります。
軽量化における注意点
軽量化にあたって注意点もあります。
・コストと性能のバランスをとる
軽量化に拘り過ぎて、高コストの材料を選定してしまうこともあります。製品の目標コスト以内に収まっているかを確認しましょう。
・環境負荷を評価する
軽量化によって、製造プロセスや廃棄時に環境負荷がかかってしまうことがあります。環境負荷も確認しておきましょう。
・材料の長期的な安定性
材料を変えることで、経年劣化しやすくなることも考えられます。劣化試験を行って確認することが必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は軽量化材料設計について解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 軽量化を行うことで、エネルギー効率などのメリットがある
- 軽量化材料には、アルミニウム合金や炭素繊維強化プラスチックなどが挙げられる
- 軽量化するときは、コストと性能のバランスなどに注意する