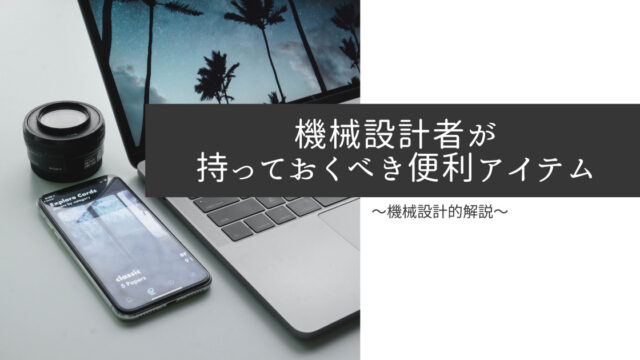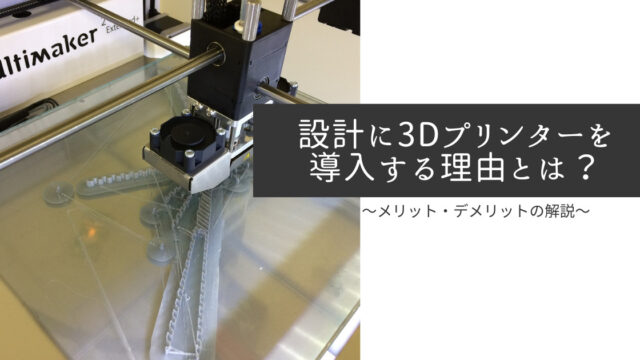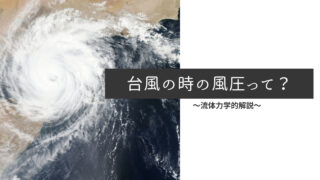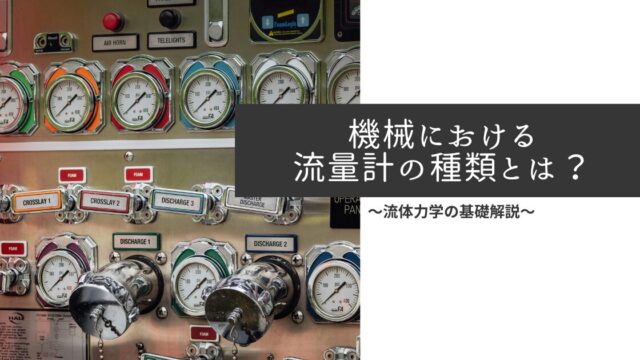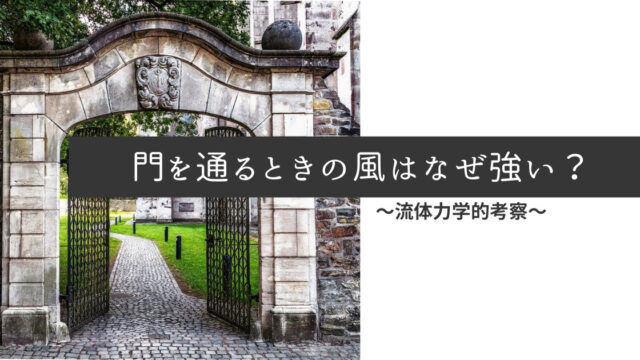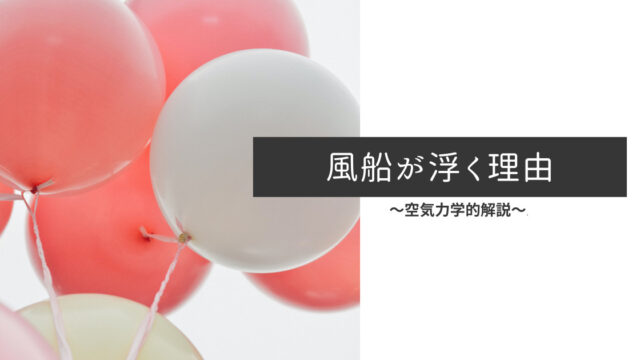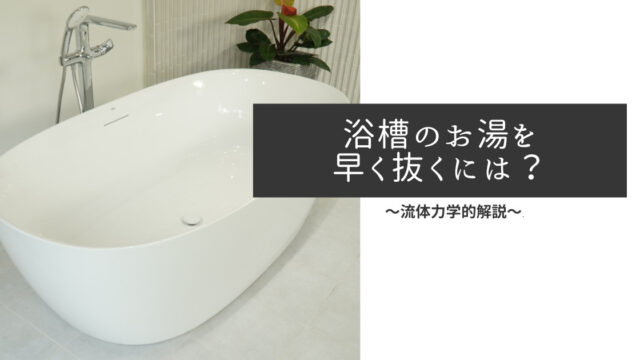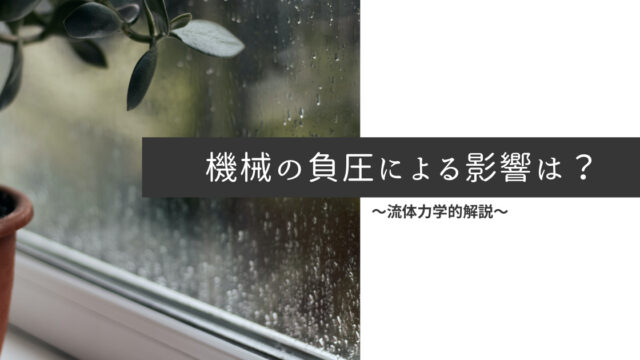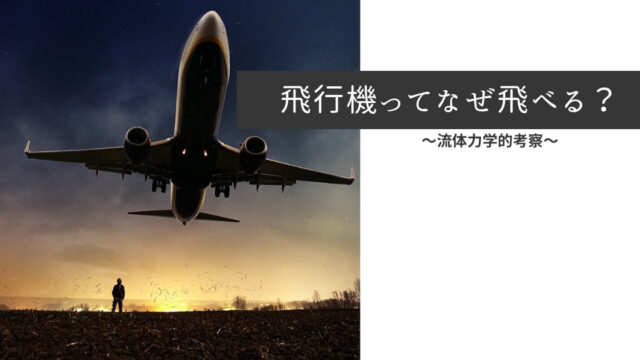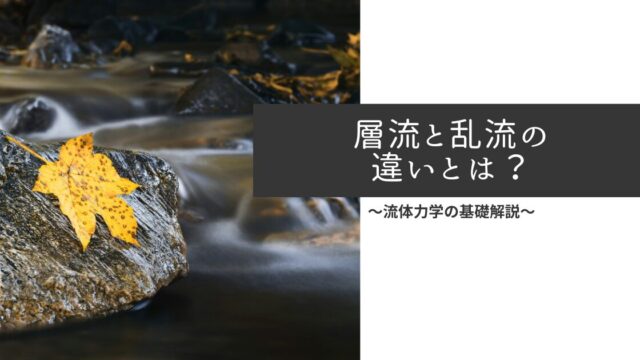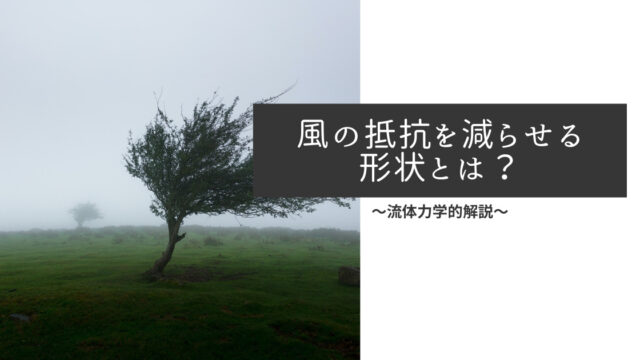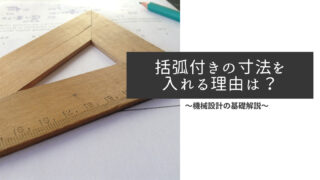動圧と静圧の違いって?【流体力学的解説】

皆さんは圧力のかかり方に種類があることをご存じでしょうか?
静圧と動圧の二つです。
ところで、この二つはどのように違うのでしょうか。
今回はこの圧力の違いについて解説していきたいと思います。
ベルヌーイの定理
まずベルヌーイの定理について説明します。
これは流体の圧力変化を表した定理になります。
数式で表すと以下のようになります。
$P+ρgh+\dfrac{1}{2}ρv^2=$一定・・・①
$P$:流体にかかる圧力[$Pa$]
$ρ$:流体の密度[$kg/m^3$]
$g$:重力加速度[$m/s^2$]
$h$:流体の高さ[$m$]
$v$:流体の流速[$m/s$]
この数式を見ると、流体の圧力は3種類あります。
そのうち、1項目の$P$と2項目の$ρgh$のことを静圧、3項目の$\dfrac{1}{2}ρv^2$は動圧と呼びます。
つまり流速よって発生する圧力のことを動圧と考えることができます。
静圧の例

例えば、ビルなどの高い場所に上ると圧力が低いということを聞いたとはありますか?
これは、高い場所であるほど、自分の頭上にある空気が少ないため、押される空気に力が弱くなって圧力が小さくなっています。
また、気体の場合には状態方程式によって、圧力が変わることも知られています。
$PV=nRT$・・・②
$P$:気体の圧力[$Pa$]
$V$:気体の体積[$m^3$]
$n$:気体の物質量[$mol$]
$R$:気体定数[$J/(K・mol)$]
$T$:気体の絶対温度[$K$]
気体の体積$V$と物質量$n$が一定と考えると、気体の温度によって圧力は依存します。
例えば、屋外に箱状の機械を置いた場合、ゲリラ豪雨などで機械内部の温度が下がったとき、圧力は下がります。
このように温度変化による圧力の影響を考えるときなどに、静圧の考え方は利用されています。
動圧の例
例えば、強風が吹いていると、空気に押されているような感覚があると思います。
これは空気の動圧によって力が働いていると考えることができます。
力の大きさは、式①の3項目の$\dfrac{1}{2}ρv^2$の値と、風を受ける部分の面積の積になります。
この動圧は、風から受ける荷重の影響を考慮するとき利用されています。
ちなみに台風の時の風で受ける圧力は、以下の記事で解説しています。
動圧と静圧の関係
この動圧と静圧には関係があります。
その関係が式①で表したベルヌーイの定理です。
関係式の見方を変えると、”静圧+動圧=一定”と考えることもできます。
つまり静圧が大きくなれば動圧も小さくなり、動圧が大きくなれば静圧も小さくなります。
例として、野球のようなボールをまっすぐ投げるときを考えてみましょう。

ボールの速度が遅い場合、重力の影響が大きいので、すぐ落下してしまいます。
一方でボールの速度が速い場合、意外と遠くまで投げられるのではないでしょうか。
これは、ボールが回転しているため、ボールの下面の動圧が小さくなり、静圧が大きくなります。
一方でボールの上面は動圧が大きくなるので、静圧が小さくなります。
するとボールの上下で静圧に差が生じるため、ボールが浮き上がるような圧力が発生し、ボールが落ちにくくなります。
これが速いボールが落下しにくい理由です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は動圧と静圧の違いについて解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 圧力は大きく分けて2種類に分類される
- 流速に影響する圧力を動圧、影響しない圧力を静圧と呼ぶ
- 静圧と動圧は、和が一定になるという関係がある