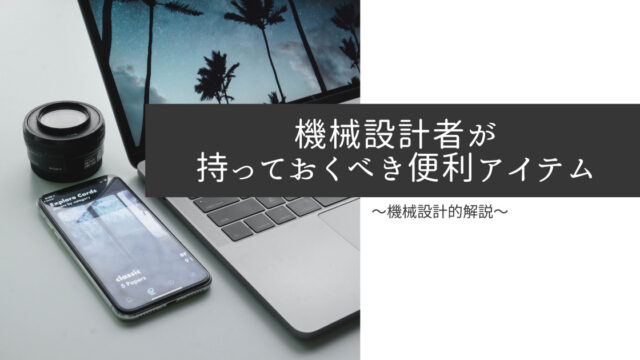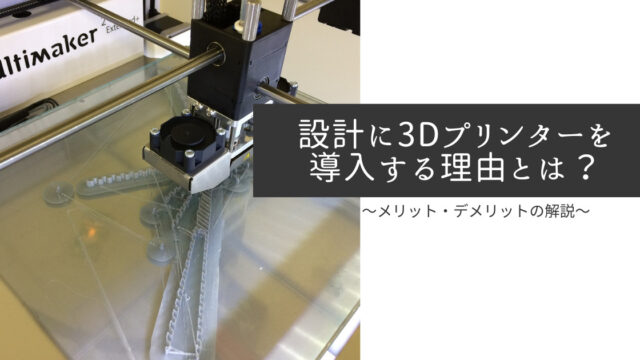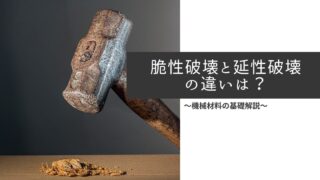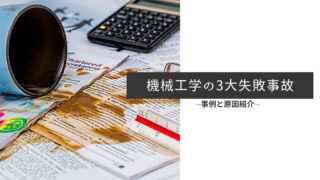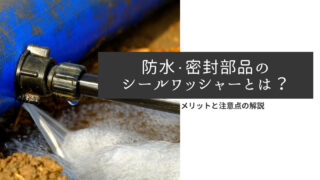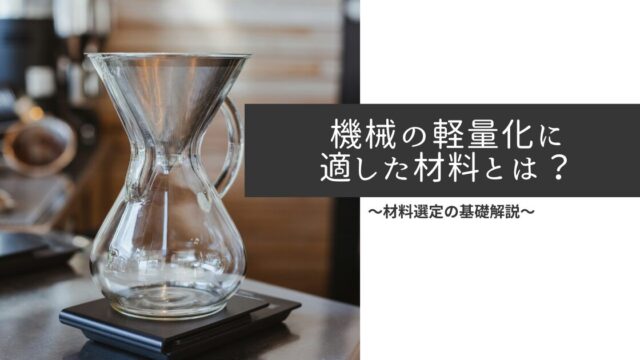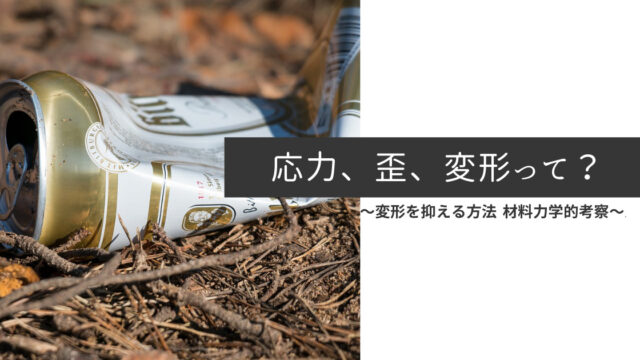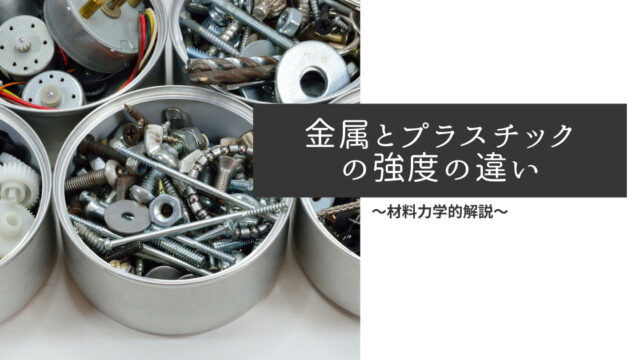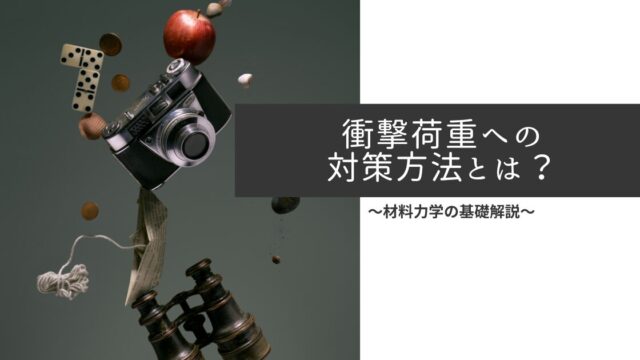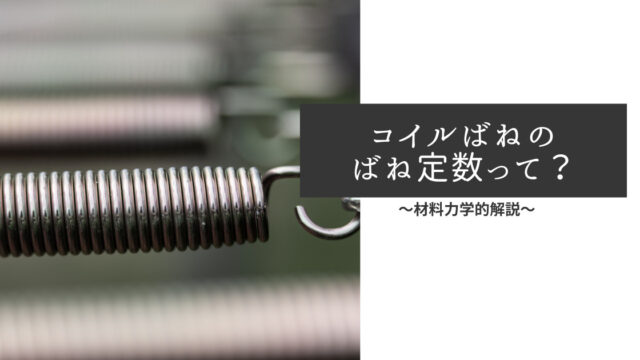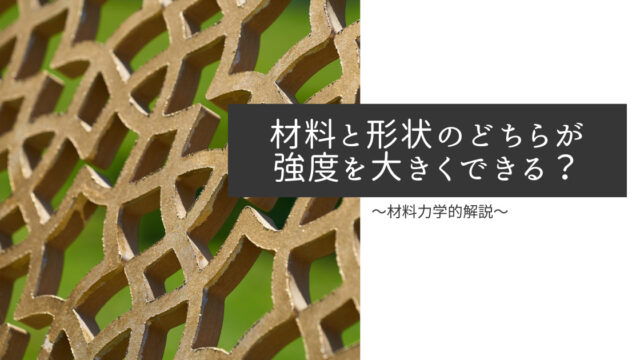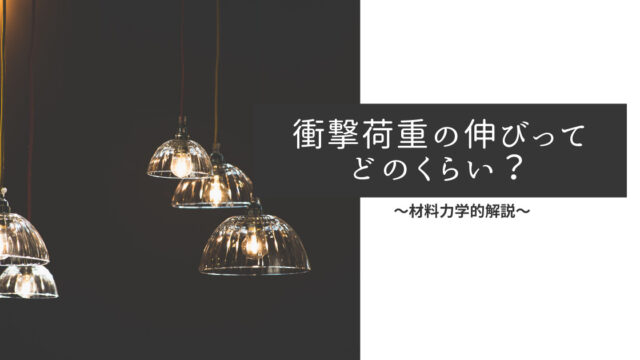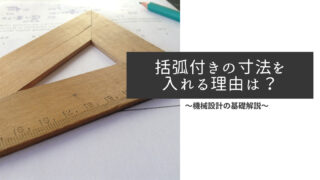材料の破壊靭性とは?【材料力学の基礎解説】
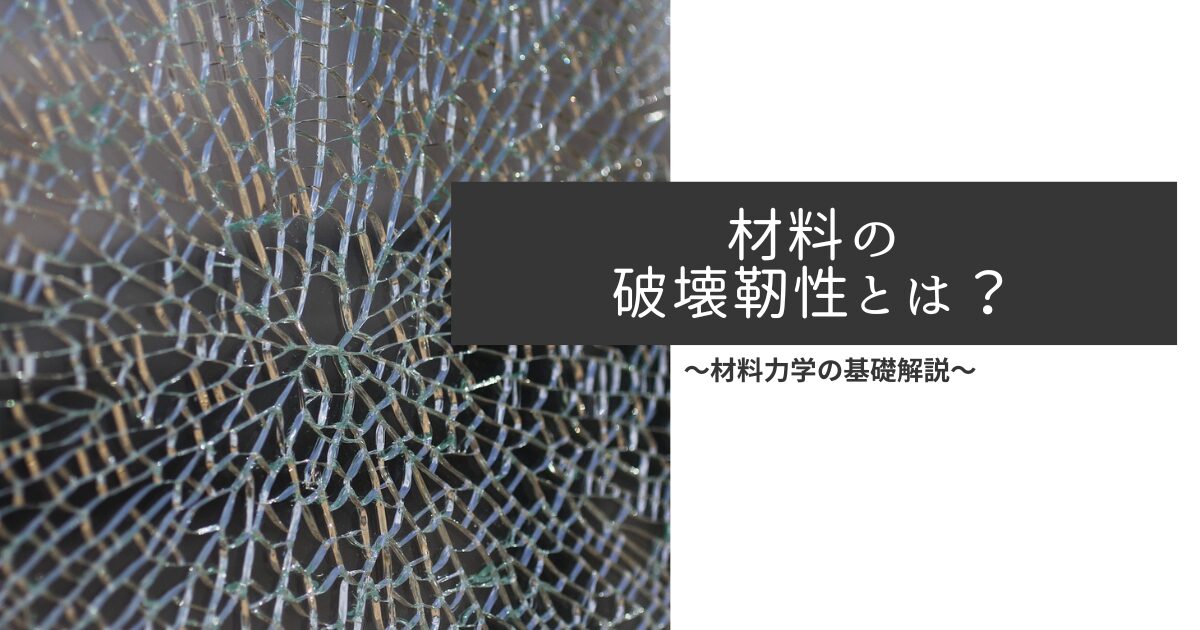
皆さんは破壊靭性という言葉を聞いたことはありますか?
機械設計において破壊靭性は重要な特性の一つになります。
今回は、破壊靭性の基本と、脆性破壊のリスクおよび回避策について解説していきたいと思います。
破壊靭性とは何か?
破壊靭性とは、材料がひび割れなどの欠陥を抱えた状態でも、破壊に至らずにどれだけ耐えられるかを示す指標のことです。
代表的な評価指数は$K_{IC}$(破壊靭性値)で表されます。
単位は$Pa・\sqrt{m}$となります。
ひび割れの先端部の応力拡大係数の臨界値であり、この値を超えると急激に破壊が進展するという境界値になります。
破壊靭性が重要な理由
破壊靭性は、以下のような場面で使用されることがあります。
- 飛行機や橋のような壊れたら命に関わる設計
- 低温でもろくなった金属を使用する装置
- 溶接部など、微小なクラックが避けられない部品
材料が破壊靭性値を超えると、脆性破壊が発生します。
この脆性破壊は、延性破壊と異なり、ほとんど変形せずに突然破壊が発生します。
そのため、事前に異常を察知できないため、設計段階での対策が重要となります。
脆性破壊を防ぐ設計方法
脆性破壊を防ぐためには、以下のような方法があります。
破壊靭性の高い材料の使用
以下のような材料は破壊靭性値が高く、脆性破壊しにくいことが知られています。
- オーステナイト系ステンレス鋼(一般材で約350$MPa・\sqrt{m}$)
- アルミニウム合金(一般材で約30$MPa・\sqrt{m}$)
- 構造用炭素鋼(一般材で約100$MPa・\sqrt{m}$)
一方で、セラミックや銅などは破壊靭性値が低いことが多いため、使いどころを選ぶ必要があります。
応力集中を避ける
ひび割れ部分に応力が集中しないように、形状を工夫する必要があります。
例えば、角部分を直角ではなくR形状(フィレット)を入れる、キー溝や切り欠きの位置を分散することが挙げられます。
使用環境に合わせた設計
材料は温度や環境によって破壊の仕方が変わります。
例えば金属の場合、低温のときは金属が脆くなり、脆性破壊が発生しやすくなります。
一方で高温の時は延性破壊が発生しやすくなります。
また、湿気や塩分のある場所では腐食によって破壊が加速することもあります。
使用環境に応じて、温度変化た湿気・塩分が直接影響しないような設計が必要となります。
破壊力学設計の導入
近年では、破壊力学に基づいた設計を行うこともあります。
例えば、$K_{IC}$を用いて安全率を計算することや、初期欠陥状態のサンプルでの破壊評価が挙げられます。
実際の破壊事例
過去には以下のような脆性破壊の事例がありました。
・リバティ船の船体破壊
溶接材を用いた船を低温の海で使用したことにより、破壊が発生しました。
・スペースシャトル・チャレンジャー号の爆発事故
Oリングが硬化し、脆性破壊したことからシール性能を失ったことでガス漏れが発生し、爆発事故に繋がりました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は材料の破壊靭性について解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 破壊靭性は、材料の欠陥に対してどれだけ耐えられるかの指標
- 脆性破壊は予兆がなく、設計段階の対策が重要
- 応力集中や設置環境の配慮が必要となっている