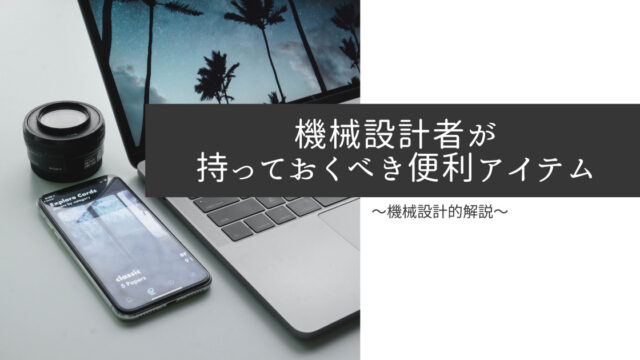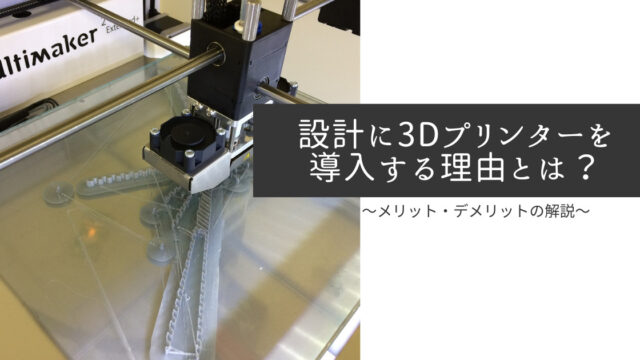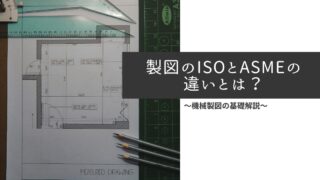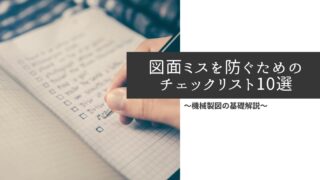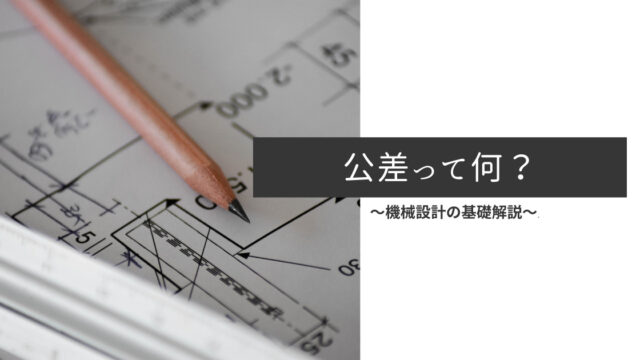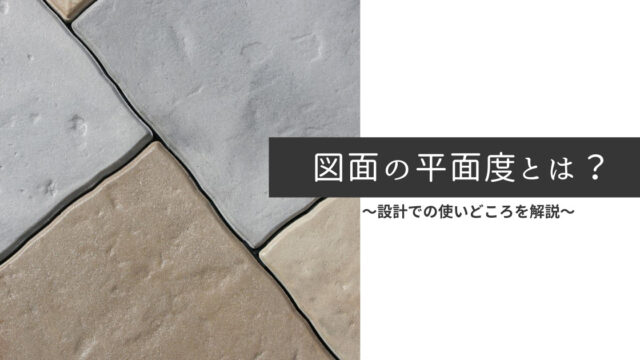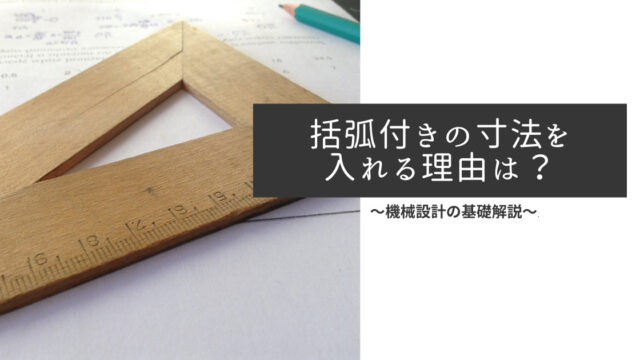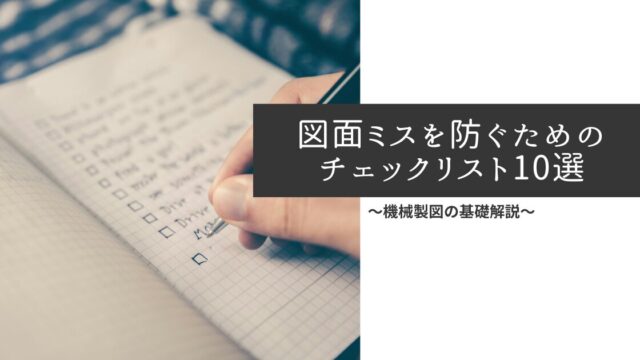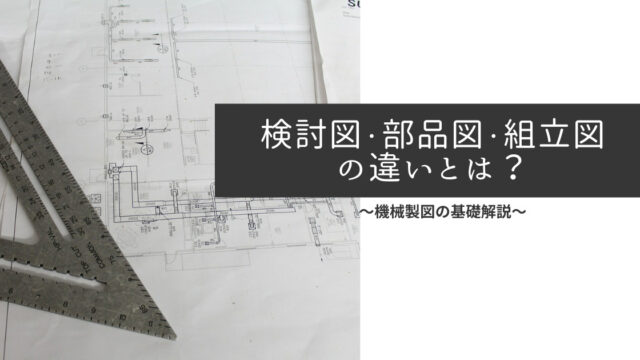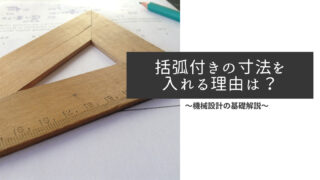3D CADと2D図面の使い分けとは?【機械製図の基礎解説】
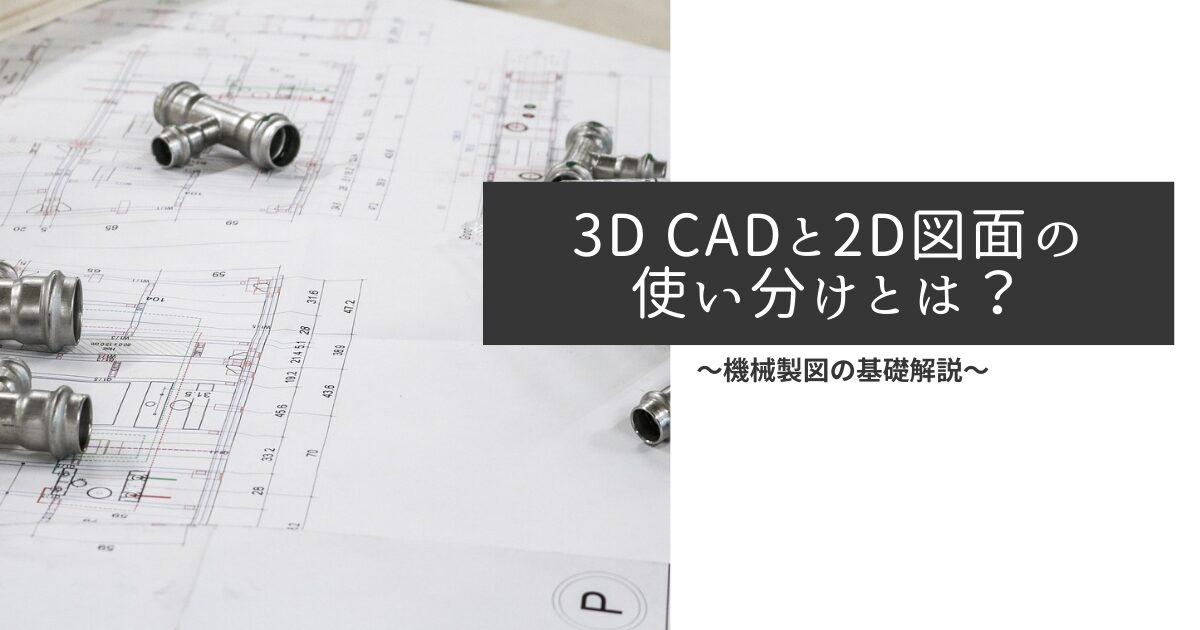
皆さんは3D CADと2D CADのどちらを主に使っていますか。
近年では3D CADが主流ではあるものの、2D図面にも不可欠な役割があります。
両方を使い分けることで、設計業務の効率化にも繋がります。
今回は、3D CADと2D図面に特徴と使い分けについて解説していきたいと思います。
3D CADの特徴
3D CADは立体モデルで直感的に形状を把握できます。
例えば、図面を全く見たことがない人に対して、製造図を渡したとしても、形状を把握することは難しいと思います。
しかし3D CADであれば、モデルの方向を変えることで、360度のあらゆる角度から形状を確認することが可能です。
また、組み立て干渉や動作シミュレーション、CAE解析など様々な機能と連携させることが可能です。
3D CADのメリット
3D CADのメリットには、以下のような点があります。
- 関連部門と形状を共有しやすい
- CAEやCAMと連携しやすい
- 顧客説明にも有効
このよう設計だけでなく、形状を把握しやすく、解析や他部門とも連携を取りやすいというメリットが大きいです。
3D CADのデメリット
一方で3D CADには以下のようなデメリットが存在します。
- データが重く、共有に時間がかかる
- 操作に高スペックPCが必要
- 製造現場では、まだ図面は必要
3Dという大きい情報を扱うため、データが重くなってしまいます。
操作にも高スペックPCが必要なので、扱いには初期費用が必要になります。
さらに、公差や素材、処理の情報を明確化するため、製造現場では、図面はまだ必要な状態です。
2D図面の特徴
2D図面は、部品寸法や加工指示を明確に伝えるためのツールです。
統一された規格に基づいて、各方向から見た図を記載します。
2D図面のメリット
2D図面には、以下のようなメリットがあります。
- 加工や検査に必要な寸法情報を伝えられる
- 加工現場での視認性が良い
- データ容量が小さく、共有が容易
寸法や素材などの情報が詳細に記載されているため、加工現場では理解しやすい図となっています。
また、図の中に全体図が記載されており、印刷して共有が容易です。
2D図面のデメリット
一方で、2D図面には、以下のようなデメリットもあります。
- 馴染みのない人には、形状を把握しづらい
- 3Dモデルとの同期が必要
- 断面図などの詳細図が必要
形状を正確に把握するため、決まった図の描き方があります。
これは、普段から図面に馴染みのない方は、形状把握が難しい場合があります。
また、3Dのデータと2Dのデータに違いがあると、ミスの原因となります。
頻繁に同期を行うことが必要です。
3Dと2Dの使い分け
ここまでで3D CADと2D図面にはそれぞれ得手不得手があることが分かったと思います。
それでは、どのように使い分けたらいいでしょうか。
3D CADを活かす場面
まず設計の初期は3D CADを用いることが多いです。
コンセプトモデルや配置検討を行うときに3D CADを使用します。
形状が固まったら、干渉チェックやCAE解析にも適用可能です。
顧客や関連部者への説明にも3D CADを活用して説明しましょう。
2D図面が必要な場面
形状の検討が完了したら、3Dモデルを使用して2D図面を作成しましょう。
特に寸法や公差が3Dデータの内容と異なっていると、組み立てができない可能性が高くなります。
作成した図面を用いて、加工業者への説明に使用できます。
可能であれば図面を印刷して、ミスがないか確認を行いましょう。
運用のポイント
3D CADと2D図面を両方用いる場合、マスターを3Dとして扱うことが重要です。
3Dが変わったら2D図面も自動で変わるように、日ごろから同期をとっておくことが重要です。
2D図面には、加工に必要な情報を集約させます。
例えば、素材・処理の方法や注記の記載が挙げられます。
これらを2D図面にまとめておくことで、加工業者は迷わずに製造が可能となります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は3D CADと2D図面の使い分けについて解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 3D CADは見やすく、CAEなどの機能と連携が可能
- 2D図面は加工に必要な情報をまとめられる
- 3Dをマスターとして2Dと使い分けることが重要