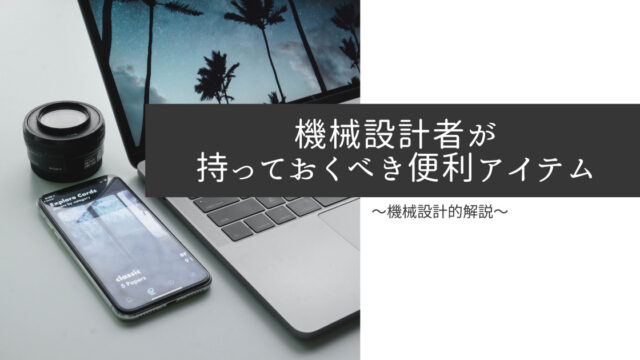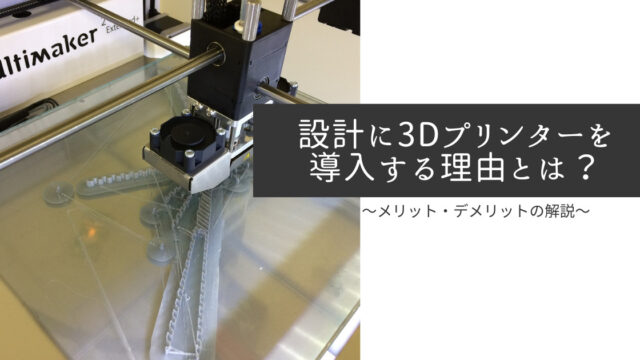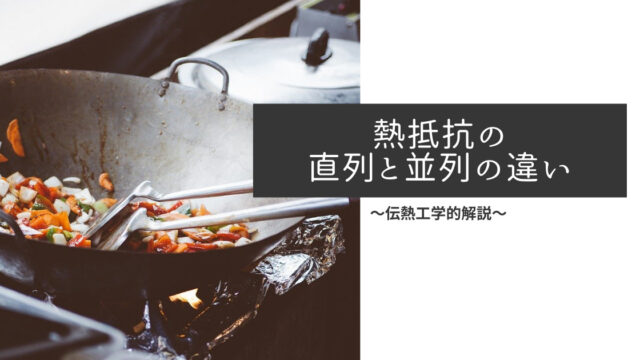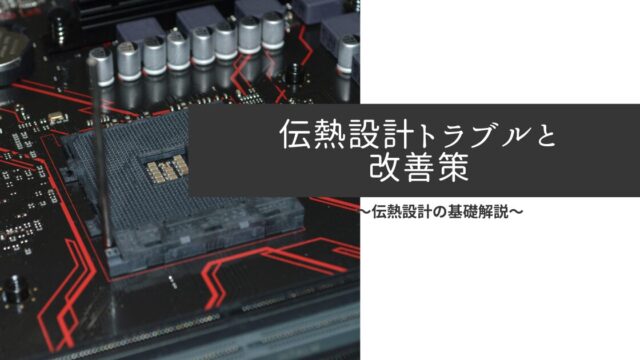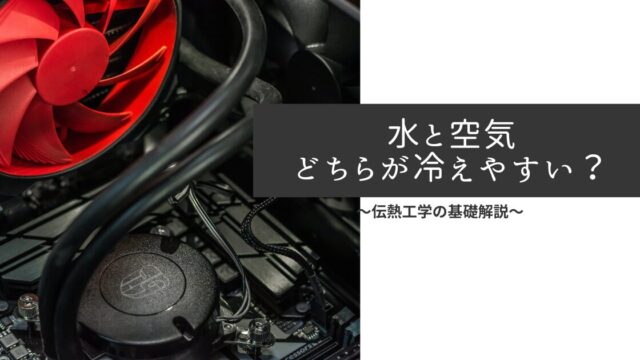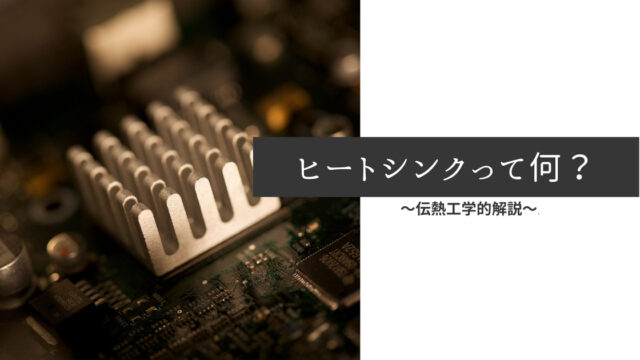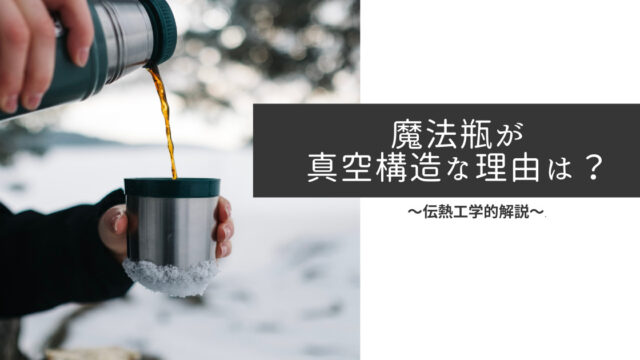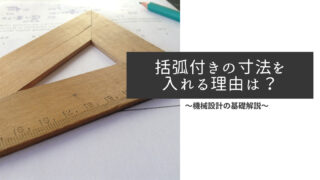熱伝達と熱伝導の違いって?【伝熱工学の基礎解説】
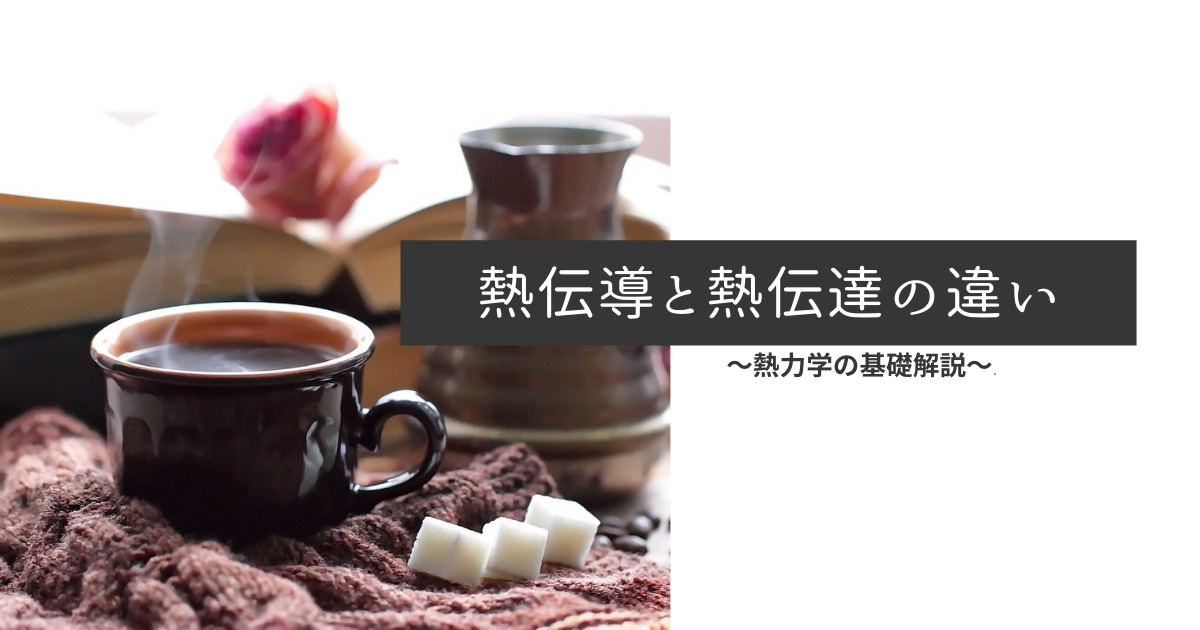
寒い時期になると、皆さんはしっかり防寒をしていると思います。
ところでなぜ寒くなると熱が奪われるのでしょうか?
今回は熱が逃げていく原因の熱伝導と熱伝達について紹介したいと思います。
放熱の3手法
物体が放熱するには、以下の3つの方法があります。
- 熱伝導
- 対流熱伝達
- 熱放射(輻射)
順に説明していきます。
熱伝導

熱伝導とは、固体中など同じ性質の物体を介して熱を伝えていく方法です。
例えば、火でフライパンを温めるとき、中央付近しか火が当たっていないと思いますが、端の部分まで熱くなっていますよね。
これが熱伝導です。
機械工学ではこの性質を利用して、熱くなった電気部品にアルミのプレートを押し当てて、熱を外に逃がすという手法を行っています。
数式で表すと以下のようになります。
$Q=k・A\dfrac{ΔT}{d}$
$Q$:物体を移動する熱量[$W$]
$k$:熱伝導率[$W/m・K$]
$A$:熱が移動する面の面積[$m^2$]
$ΔT$:温度変化[$K$]
$d$:熱が移動する厚さ[$m$]
対流熱伝達

対流熱伝達とは物体から周囲の空気や水などの流体に熱を伝えることで、流れを起こすことを指しています。
例えば、鍋で水を温めてお湯を作るとき、鍋の中のお湯が循環しているところを見たことはないでしょうか。
この現象が対流熱伝達です。
機械工学では、FANを使って発熱部品の周囲に風を起こして熱を逃がしています。
数式で表すと以下のようになります。
$Q=h・A・ΔT$
$Q$:物体を移動する熱量[$W$]
$h$:熱伝達率[$W/m^2・K$]
$A$:熱が移動する面の面積[$m^2$]
$ΔT$:温度変化[$K$]
熱放射(輻射)

熱放射(輻射)とは、発熱部から電磁波を発して受ける熱のことを指しています。
ヒーターに手をかざすと少し離れている場所でも暖かいという経験があるのではないでしょうか。
機械工学では、装置の塗装の色を変えて温度を調整したりすることもあります。
例えば、陽の光が直接当たる場所に置く装置は、太陽からの放射熱を防ぐために、外面に白い塗装をして温まりにくくする、という手法があります。
熱放射を数式で表すと以下のようになります。
$Q=ε・σ・A・T^4$
$Q$:物体を移動する熱量[$W$]
$ε$:輻射率
$σ$:ステファンボルツマン定数[$W/m^2・K^4$]
$A$:熱が移動する面の面積[$m^2$]
$T$:物体の表面温度[$K$]
熱伝導と熱伝達の違いは?
ここで、よく混同しがちな熱伝導と熱伝達の違いについて説明したいと思います。
放熱方法による違い
熱伝導は、放熱手法の「熱伝導」が起こるときに発生する現象のことを指します。
一方で熱伝達は「対流熱伝達」によって放熱するときに起こる現象です。
現象が異なるので、言葉の使い分けが必要です。
熱の伝わり方による違い
熱伝導とは、同じ性質の物体同士で熱を伝えるときに表されます。
例えば、種類が異なる金属同士で接触させて熱を伝える場合は、熱伝導に分類されます。
これは種類が異なったとしても、固体という同じ性質の物同士で熱を伝えているためです。
一方で熱伝達は、種類が異なる物同士で熱を伝える場合に呼ばれます。
例えば、固体から気体に放熱する場合は熱伝達に当たります。
もちろん、気体ではなく、水などの液体に放熱した場合も熱伝達です。
このように固体、気体、液体の間で熱のやりとりを行う場合は熱伝達に当たります。
単位の違い
熱伝導率と熱伝達率の単位にも違いがあります。
熱伝導率$k$の単位は[$W/m・K$]であり、熱伝達率$h$の単位は[$W/m^2・K$]です。
熱伝達率の方が分母に[$m$]が1個多いですね。
これは熱伝達は接触面(例えば、固体と気体の接触面など)に影響されるためです。
熱伝導も面に関係していますが、熱が通過する厚みにも影響するので、$m$が1個分少なくなります。
不変か可変か
熱伝導率は固体の種類によって決まる不変の値です。
しかし熱伝達率は周囲の流速や温度によって決まる可変の値です。
例えば、扇風機の前に立っているときと、無風のときでは体温が下がるスピードは全く異なりますよね。
このように熱伝達率は周囲の環境によって決まる値になります。
終わりに
いかがだったでしょうか。
今回は混同しがちな熱伝導と熱伝達の違いについて解説していきました。
たった一文字の違いでも意図が十分に伝わらないこともありますので、しっかりと使い分けていきましょう。
今回の内容をまとめると以下のようになります。
- 放熱の種類には、伝導・対流。放射の3種類がある
- 熱伝導は固体同士など、同じ性質の物質のとき、熱伝達は固体と気体など、異なる性質の物質のときに用いる
- 熱伝導率と熱伝達率は伝わり方や単位などの違いがある