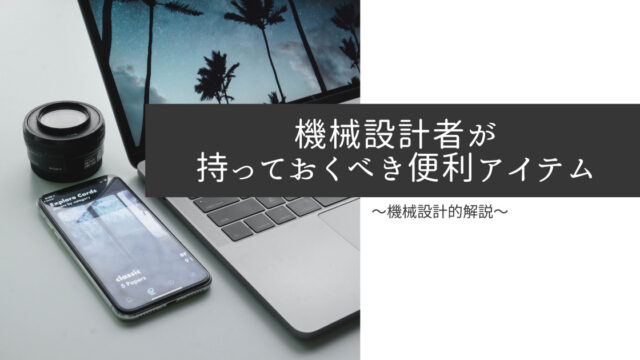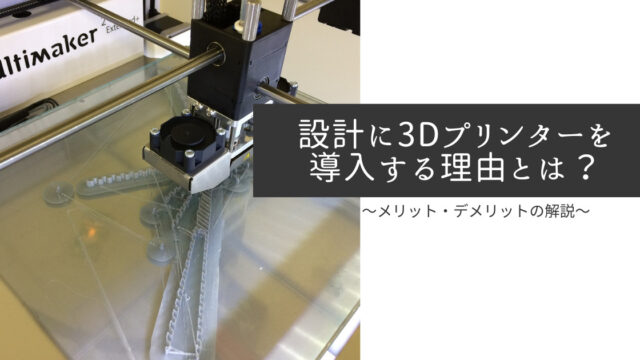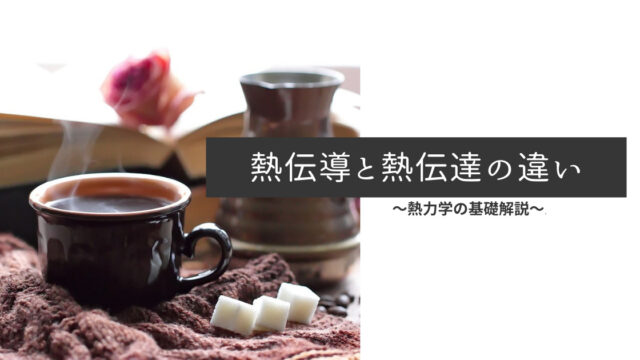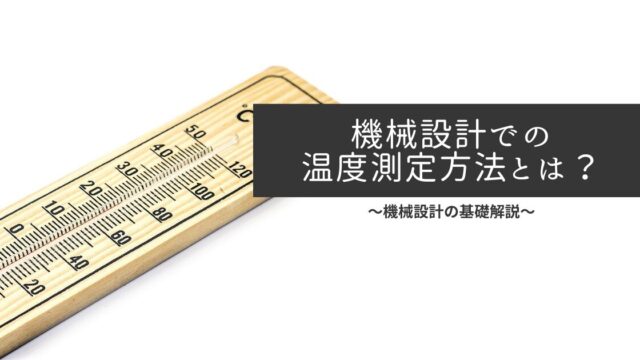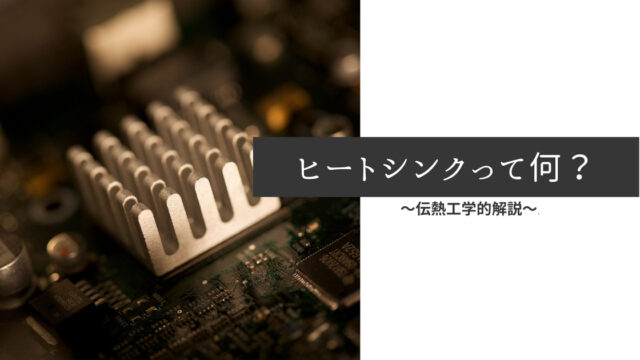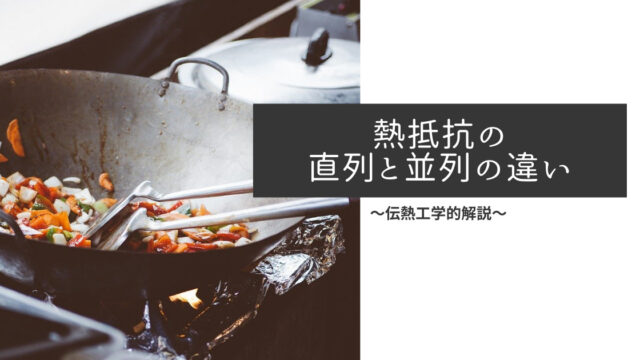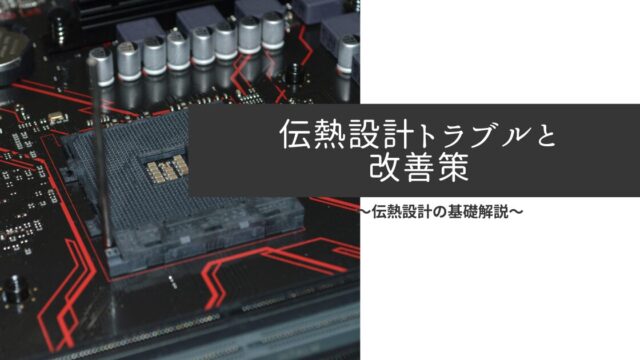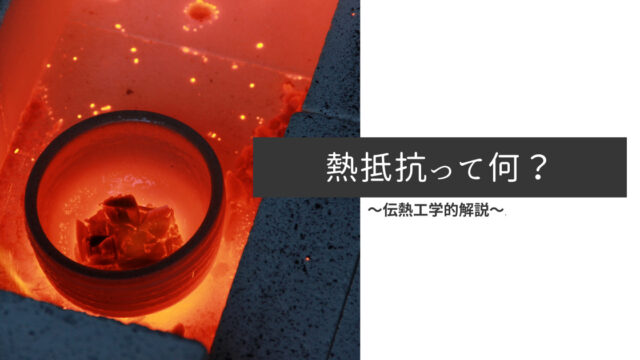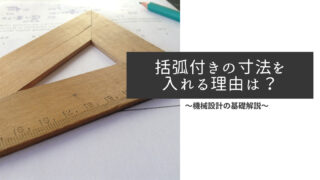空気と水はどちらが冷えやすい?【伝熱工学の基礎解説】

皆さんは、空冷や水冷のような言葉を聞いたことがありますでしょうか。
どちらも発熱する物体を冷却する方法ですが、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は空冷と水冷の違いについて解説していきたいと思います。
空冷・水冷とは?
空冷とは、空気などの気体によって冷却することを指しています。
扇風機で風を送っているようなイメージです。
一方で水冷とは、水のような液体によって冷却することを指しています。
水道で水を流して鍋を冷やすようなイメージです。
このように、冷却する方法によって、空冷・水冷と用語を使い分けています。
空冷について
空冷の例
まず、空冷には自然空冷と強制空冷の2つの方法があります。
自然空冷とは、周囲から風を送ることなく、自然対流のみで冷却する方法を指しています。
例えば、スマートフォンの内部部品などは自然空冷で冷却しています。
厳密には、発熱部品を熱伝導によってケースなどの外側の部品に熱を伝え、外側部品の熱を空気によって冷却しています。
一方で強制空冷とは、他の部分から風を送って冷却する方法を指します。
例えば、ノートパソコンの内部部品は強制空冷で冷却していることが多いです。
自然空冷と比較すると、冷却効果を大きくすることが可能です。
ただし、FANなどの冷却部品が必要になることや、騒音が問題となることもあります。
空冷のメリット
水冷と比較して空冷のメリットとして、以下のような点が挙げられます。
- 冷却剤が空気のため、入手しやすい
- 水を導入する特殊な機構が必要ない
冷却に使用する冷却剤が空気であるため、比較的入手しやすいという点が挙げられます。
例えば、熱伝導で熱を逃がす場合、熱を逃がすための特殊材料が必要となります。
家電製品などであれば、通常は空気がある場面での使用が想定されるため、入手性が良いという点はメリットとなります。
また、水を導入する機構が必要ないため、装置を小型化しやすくなります。
このため、コスト面でも水冷と比べると有利になることが多いです。
空冷のデメリット
水冷と比較して空冷のデメリットは以下のような点が挙げられます。
- 水と比較して冷却が弱い
- 空気のない場面では使用できない
水と比較すると、空気の方が冷却性能が悪いです。
これは、水道の水で熱い物を冷やすときを考えれば明らかだと思います。
理由としては、空気と比較して水の方が熱伝導率が大きいためです。
空気の熱伝導率は20[℃]で0.0257[W/m・K]ですが、水の場合は0.602[W/m・K]となるため、水の方が20倍以上の熱を伝えやすいということになります。
また、水中で使用する装置や、宇宙空間で使用する装置など、空気が周囲にない場合は空冷を使用することはできません。
特に水中で使用する装置については、水冷の方が効率がいい場合もあります。
水冷について
水冷の例
水冷の例として、高性能デスクトップPCが挙げられます。
このような装置の場合、発熱量が大きいため、空冷では追いつかない場合があります。
そのため、水を流してより大きな冷却性能が必要となります。
水冷のメリット
空冷と比較した場合の水冷のメリットは以下になります。
- 冷却性能が大きい
- 空気のない場面でも使用可能
前述した通り、熱伝導率が大きいため、水冷の方が冷却しやすくなります。
水冷のデメリット
空冷と比較した場合の水冷のデメリットは以下になります。
- 水漏れによる故障の恐れがある
- 機構が複雑になる
冷却したい部品が電気部品の場合、もし水漏れが起こったら故障してしまいます。
そのため、水冷を行うためには水漏れが起こらないよう細心の注意を払う必要があります。
また、空冷の場合と比較して、水を流して冷却するため、より機構が複雑化してしまいます。
空冷の場合よりもコストアップは避けられない事がほとんどです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は空気と水の冷却について解説してきました。
まとめると以下のようになります。
- 空冷とは、空気などの気体による冷却を指す
- 水冷とは水などの液体による冷却を指す
- 水冷の方が冷却性能はいいが、複雑な構造になりやすい